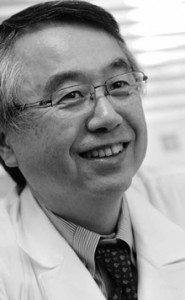 高橋和久(たかはし かずひさ)
高橋和久(たかはし かずひさ)
順天堂大学医学部附属 順天堂医院 呼吸器内科 教授
1992年、順天堂大学大学院卒業後、94年から米国ハーバード大学医学部附属マサチューセッツ総合病院がんセンター留学。帰国後、順天堂大学医学部呼吸器内科講座講師などを経て、2005年8月、同大学医学部呼吸器内科学講座教授、同大学大学院医学研究科呼吸器内科学主任教授に。主な著書に、『世界で一番やさしい肺がん』(エクスナレッジ)など。(取材時現在)
医師が、患者さんのQOLではなく自分のQOLを優先しているようではいけない――。
がん治療の最前線、最も困難とされる肺がんと闘う高橋氏を支えるのは「最も治らない病気を治したい」という熱い気持ちだった。
肺がん治療の現状から最新の研究、さらには、「医師の本分」に迫った。
肺がんは死亡率が一番高いがんと恐れられている。しかし、「ここ5年間ほどで大きく変化し、パラダイムシフト、すなわち劇的な転換期を迎えています」と高橋和久は語る。穏やかな語り口の中に、人を包み込むような優しさと信頼感が滲み出る。
祖父も父も医師だった。医師の遺伝子が継承され、その魂が開花しているのだろう。
なぜ、肺がんの医師を志したのか。「がんの中でも最も退治しにくいがんですからね。難攻不落の山に挑みたいと思いました」
呼吸器内科専門臨床教室としては日本で最も伝統のある順天堂大学大学院の主任教授として、「研究・臨床・教育」の3分野に携わる日々は、まさに寝食を忘れる忙しさだ。
「睡眠時間が4時間を切る日が続くと辛いですが」
笑いながらも、背筋を正して、「医師にとって患者さんは、最大の教師です」という。中学から大学まで剣道をやってきた「文武両道の精神」が身についているかのようだ。
従来、肺がんは「非小細胞肺がん」と「小細胞肺がん」の二つに大別され、それに適した薬が使われてきた。ところが最近、がんを引き起こすさまざまな遺伝子の異常を、治療の前にあらかじめ調べることが可能になった。
「同じ非小細胞肺がんであっても、ある遺伝子の異常で起きたがんと、まったくそれとは異なる遺伝子の異常で起きているがんがある。発がんのメカニズムが異なるものが、非常に多くあることがわかってきました。その異常を正すような薬も開発されています」
つまり、がんの遺伝子情報に応じて、がんの治療法を選択する「個別化治療」の時代が到来したのである。肺がんは「個別化治療」によって、「一番恐ろしいがん」ではない時代となったのか――。
「残念ながら現在でも、肺がんと診断がついた時点で手術ができるのは、約3〜4割。残り6〜7割の方は、治療のゴールド・スタンダードである手術ができない進行がんなのです」。いかに早期発見が重要かということだ。
初期(1期のA)の段階で発見できれば、「手術後の5年生存率は85%以上」だという。
「この時点ならほとんど根治することが可能なわけですね。ですから、まず早期発見診断の技術を開発し、治る段階のがんを手術にもっていくこと。それと同時に手術のできない患者さんに対する新しい薬や治療を開発していくこと。この2本立てが必要です」

