医師に大切なのは医学の知識や技術だけではなく、「人間への興味だ」と金子はいう。
臨床の現場はもちろん、基礎研究に熱中しているときにも、その眼差しの先には人間がいる。
人の役に立つ医療を目指す——。
この熱い思いに突き動かされ、医師としての人生を力強く歩み続ける。

金子周一(かねこ・しゅういち)
1956年、岐阜県生まれ。82年に金沢大学医学部医学科卒業後、同大学の大学院へ進む。卒業後、金沢大学附属病院第一内科へ。内科全般に加え、消化器内科において、肝臓病や消化器がんの治療で高度な医療を実践。科学技術では2013年に発明賞、14年に文部科学大臣賞表彰を受賞。04年と15年に新しい診断法の開発で、それぞれ文部科学大臣、経済産業大臣の産学官連携功労者表彰を受ける。11年より日本消化器病学会理事を務める。(取材時現在)
2016年8月に還暦を迎えたが、仕事量は増え、忙しさは増すばかりだ。早朝の会議から始まって、夜7時ごろまでは院内業務をこなし、その後も外部の会議や会合が続く。土日もほぼ仕事で、「そういえば、今週は1度も家で夕食を食べていないなぁ」とポツリ。後輩医師からは、「金子先生ほど多忙だったら、僕たちは倒れてしまいます」との声が聞こえてくる。誠実で真面目、勤勉、それが金子を形容するのにふさわしい言葉だ。
だが、「大学時代は勉強とは無縁」と金子は40年前を振り返る。留年こそせずにすんだが、クラブにも入らず、アルバイトや遊びばかりしていたから、成績はかんばしくなかった。「医学部に入ったのだって、少し勉強ができて理系に強かったから。大それた志をもって医師になろうと思ったわけではないんです」と苦笑する。
実習授業にも熱が入らなかった。
「実習なんか早く終えて遊びに行きたいという欲求のほうが強かったから、当然よい実験結果も得られない。よいレポートに仕上がるわけありませんよね」
ところが医学部を卒業し、消化器内科で診療に当たると金子は俄然(がぜん)仕事人間に。何が彼を変えたのか——。
「責任の重さを再認識したということもあったでしょうし、学生時代から仕事熱心な教授や諸先輩たちの姿を見ていて、社会に出たら自分もあの後に続くんだと、無意識のうちに覚悟を決めていたのかもしれません」
医師という仕事には「理系の知識」だけでなく、「人間への興味」が必要と気付いたことも理由の1つかもしれないと話す。
洋画などによく登場するカウンセリングのシーンに憧れた金子は、実は精神科医になりたかった。
「患者さんの家庭環境や人間関係、悩みなどを聞いて病気の本質を探ることに興味がありました」
進路選択を前に、その希望を先輩に告げると、「君のやりたいことは、精神科医より、むしろ内科医の領域」とのアドバイスを受けたため、内科医としての道を選択した。故郷の岐阜県郡上市で商売を営む両親は、歯科医に将来性を感じ、「息子を歯科医にしたい」と考えた。名古屋に開院のための土地まで購入したが、金子は自分の希望を通した。
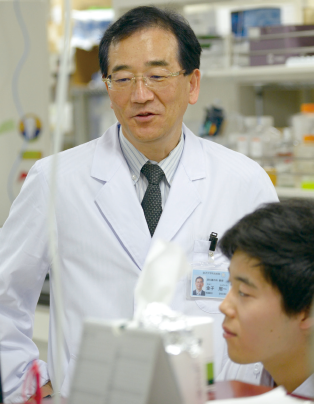
実際に内科医になってみると、そこには金子が望んだ領域が確かにあった。患者さんの話を聞き、背景にあるストーリーを知ったうえで病気と闘う。がんのように治療が長引いたり、完治が難しかったりする病気の場合、特にコミュニケーションが欠かせない。
ただし、金子はこれだけに満足しなかった。企業との共同で遺伝子やがんの研究に尽力し、2009年には、胃がん、大腸がん、膵がんの有無を血液で判別する遺伝子群を世界で初めて突き止めた。こうした功績が評価され、産学官連携功労者にも選ばれている。さらに、自らの手で薬も開発していきたいと抱負を語る。「海外で開発された薬にばかり頼っていたら、日本はどんどん貧してしまう。海外に輸出して日本が潤うような新薬を生み出していきたいんです」と、どこまでも意欲的だ。


