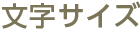リンパ節や臓器を切除する従来の手術は、臓器を残す方向を目指して改善されていきます。
食道がんは、早期発見されれば内視鏡治療でがんを切除できるが、がんが粘膜を越えて進行している場合は、7〜8時間もかけて、食道すべてと周囲のリンパ節を切除し、代わりに胃を細長い筒状にしてのどの部分につなぐ。周囲にある心臓や気管、肺といった重要な臓器に負荷を与えないように、細心の注意を払わなければならない。難易度の高い手術だ。
「1950年ごろ、当時千葉大学第二外科教授だった中山恒明先生の手術法により、食道がんの手術による死亡率(手術後1カ月以内の死亡)は10%を切りました。当時の手術死亡率は20〜60%でしたから、先生は世界的な外科医として称賛されました。そして現在は1%。我々は、手術死亡率ゼロを目指し、手術の安全性、根治性、患者さんのQOLの向上のために、『よりよい手術』をモットーにしているのです」
がんの手術は他の手術とは違う。たとえば、白内障の手術をすれば、見えない眼が見えるようになる。
「ところが、胃がんを治すためには、患者さんは、そのメリットと引き換えに、胃を失うというデメリットを受け入れざるを得ないことが多い。でも、胃を残すことができれば、患者さんのデメリットは軽減されます」
これがまさしく「よりよい手術」。胃のどの部分にがんが潜んでいるかを的確に見極めることができれば、正常な胃の部分を残すことが可能になる。その技術を開発するために、瀬戸は産学協同プロジェクトによる「最先端研究支援プログラム」に参加している。
瀬戸の実直な語り口と、その風貌には、穏やかで力強い東北人の雰囲気が感じられる。「秋田生まれ。県立秋田高校から東大の医学部へ進学したのです」。父は外科医で、病院を経営していた。父の背中を見て育ったので、迷うことなく外科医の道へ。
「父は土、日もなく患者さんを診ていました。私も同じです」

毎朝の回診、週3回の手術などの「臨床」に加え、医学部消化管外科学教授としての「教育と研究」。この3分野に携わる仕事漬けの日々を瀬戸は、むしろ楽しんでいるように見える。
33歳のときに国立がんセンターでチーフ・レジデント(がん専門修練医)を務め、1年間、手術に明け暮れた。その修練の日々が、手術の達人・瀬戸の原点だ。
「まったくの無趣味。趣味は仕事でしょうか」
自宅は病院から徒歩15分という近さだ。家庭は、秋田美人で才媛、と噂される夫人が守る。中学から大学までバスケットの選手として活躍した文武両道の熱血漢は、照れながら「いつも妻に感謝しています」と微笑む。
「とても気のつく聡明な人で、僕の海外出張の準備なども完璧にしてくれます。会う人や会食などを質問され、スケジュールを伝えれば、洋服などもバッチリそろえて荷物をつくっておいてくれます」
洋服も自分で買ったことがない。すべて愛妻の見立て。長女は父と同じ道を進み、やはり東大病院に身をおく。医師の志と情熱は、しっかりと受け継がれている。
瀬戸は、近年とみに「集学的治療の大切さ」を思う。集学的治療とは、外科手術だけではなく、薬物療法、放射線治療など、さまざまな手法を組み合わせて治療に当たること。「以前なら、発見された時点で、手術すら不可能とされていた高度進行がんの患者さんにも、いろいろな治療法を組み合わせて対応することができるようになりました」
手術でがんが除去できた場合は、その組織を使った樹状細胞ワクチン療法で再発を防ぐ。「ダ・ヴィンチ」と名付けられた医療ロボットによる手術も行われている。瀬戸が率いる病棟でも大学の教室でも、日々、挑戦と進化が続いている。
(敬称略)