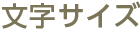最先端の医療技術に光を見いだし、研究と診療を続けていきたい。
医師の家系ではない。両親も、中島が医師になるとは想像もしていなかったらしい。「私自身もなぜ医師を目指したのか、明確な理由は思い当たりません。ただ幼いころは病弱で、よく病院に連れて行かれた。そのときのお医者さんが怖くて……。医師に対して悪いイメージしかなかった。だから、もっと患者さんに安心感を与える医師になりたいと目指したのかもしれません」
ハードルが高ければ高いほど燃えるタイプ。呼吸器外科は、肺がんをはじめ手ごわい病気が多いため、なかなか医師のなり手のない分野なのだ。東大病院の医局で、呼吸器外科専門の医師が自分一人だったこともある。
「あまのじゃくなのでしょうねぇ。他の人の敬遠するような難しい問題と向かい合うのが好きなんです。だから、自分のやっていることに満足しています」とはにかむ。
肺がんを治すのがなぜ難しいのか。X線検査で肺がんが発見された時点で、手遅れになっている場合が少なくないからだ。現在ではCTなどによる高精度の検査技術が普及したが、それでも厚生労働省の2012年の調査では、日本の年間死亡者数約120万人のうち、肺がんで亡くなる人は約6%を占める。
「一人でも多くの患者さんを助けたい」と切望する中島は、最先端医療の可能性にも偏見なく向き合う。その一つが免疫細胞治療だ。東大病院呼吸器外科では、中島を中心に、先進医療としてがん免疫細胞治療の臨床研究に取り組んでいる。標準的な抗がん剤治療で効果が得られずに、有効な治療法がなくなってしまった患者さんが対象だ。
「人間の白血球の中にあるリンパ球には、がんを攻撃する力があります。なかでもガンマ・デルタT細胞は、がん細胞に対する多角的な攻撃手段を備えています」
中島たちは患者さんの血液を採取し、ガンマ・デルタT細胞を取り出して培養。再び患者さんの体内に戻すという治療を行っている。この治療は、肺がんの患者さんすべてに効果があるわけではない。
「ただ、自分の血液を使うので副作用が少ないという利点がありますし、この治療を受けたほとんどの患者さんの病状も安定しています。つまり、完治はしないが、がんも、これ以上育たない。さらに有効な方法を解明するために臨床研究を続けていく意義があると考えています」
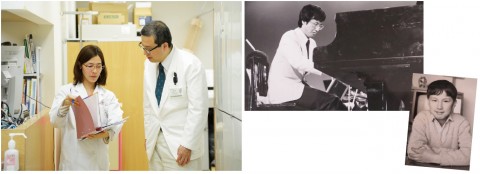
一つひとつの言葉を吟味しながら語る姿に、誠実な人柄が垣間見える。しかも一心に取り組む気質は、仕事だけでなくプライベートも同様だ。
例えば趣味のピアノ。学生時代には、ヤマハの講師資格認定試験を受けて、講師の免状も取得した。今も大学医学部のピアノの会の顧問を務め、毎年、五月祭には学生とともにステージに立つ。そのため、週末に学会のないときには、できるだけピアノの練習をする。「存分に練習できる時間は、なかなか取れませんが、1年に1曲、新しい曲をマスターするのが目下の目標です」。スクリャービン、カプースチンなど、ロシア系の音楽家が好みだ。
健康のために始めたタウンウォーキングもとことんやる。ここ数年で文京区内のどんな細かい道も踏破。他人の家の庭にまで入り込みそうなくらい、徹底的に歩くらしい。
目標を決めたら、躊躇(ちゅうちょ)なく突き進む。そのタフな仕事ぶりに、思わず「疲れないのですか」と質問を投げたら、中島が笑顔で答える。「常に激しく、楽しく疲れています」。仕事も遊びも挑戦することに喜びを見いだす。そのひたむきさに救われた患者さんは決して少なくない。
(敬称略)